解説協力:Schumpさん
怪人三七型さん
ささきさん
釜屋庄多朗さん
怪人三七型さん
ささきさん
釜屋庄多朗さん

(2007/4/12更新)
ジェフリー=デハヴィランドの設計になる英国初の本格的単座戦闘機。設計時に実績をあげていたヴィッカースFB5などのプッシャー式複座多用途機の設計思想を継承したため、機首のルイス機銃は陸戦型と同じピストルグリップを有し、可動式のマウントに取り付けられていた。しかし、専任の射手なしで操縦と照準とを別々に行う不便を看過できなかったことから、前線ではマウントをロックした固定式機銃として使われることが多く、火力集中のために連装とした機体もある。実戦テスト中の試作機が独軍に鹵獲されるという不運に見舞われながらも、前線配備当時の最強戦闘機であったフォッカーE.IIIに対して、高高度ではほとんど差がなくなるとはいえ、速度と上昇力でわずかに勝り、旋回性能では優位に立っていたため、1916年夏から、独軍にアルバトロスD.IIが充足する同年晩秋までの短い期間ながら、西部戦線の制空権を拮抗状態にまで回復する立役者として活躍した。第一線を退いてからも中東戦線などでは戦力として存在感を示し、本土では防空戦闘や戦闘機搭乗員養成にWW1終盤まで重宝された。生産数は401機。
アイコンは、英陸軍航空隊第24飛行中隊所属の機体。同隊は、英軍初の単座戦闘機だけで構成された飛行中隊として多くの戦訓を残し、後の英空軍創立の礎となった歴史的な存在である。
アイコンは、英陸軍航空隊第24飛行中隊所属の機体。同隊は、英軍初の単座戦闘機だけで構成された飛行中隊として多くの戦訓を残し、後の英空軍創立の礎となった歴史的な存在である。

(2007/4/12更新)
もともとはフランク=バーンウェルらブリストル社若手設計者の手になる小型競技用機であったが、欧州情勢の緊迫にともない、英陸海両軍に採用された。WW1緒戦期の機体としてはトップクラスの速度・上昇力・運動性を誇ったことから、本来の強行偵察以外にも、写真偵察、機銃を積んでの対飛行機戦闘、ダーツによる対気球・飛行船戦闘などにも活躍した。英国初の同調式機銃搭載機であり、世界で初めて艦船の飛行甲板及び他の航空機からの発進に成功するなど、航空技術史上にも足跡を残している。しかし、高機動の機種に対応した訓練課程が未整備だったために事故損失が多く、また、戦闘機としての集中運用がなされなかったことから対空戦闘における戦果も個人的なものにとどまっている。さらに、機体が小型軽量で高出力エンジンや大型弾薬箱の装備が困難だったことや、生産中の頻繁な改修のせいで部品の互換性を欠き、整備に混乱をきたしたことなどから、1916年半ばから次第に第一線を退いていった。しかし、飛行隊幹部クラスの中には、本機の操縦性と性能に惚れ込み、員数外の個人用連絡機として使用し続けた者もいる。生産数は374機。
アイコンは、L.G.ホーカー大尉が1915年7月に3機の撃墜戦果を挙げ、戦闘機搭乗員としては初のヴィクトリア十字勲章を授与された際の乗機。胴体左側面のルイス機銃は30度外向きに装着され、プロペラ回転面を避けて発射された。
アイコンは、L.G.ホーカー大尉が1915年7月に3機の撃墜戦果を挙げ、戦闘機搭乗員としては初のヴィクトリア十字勲章を授与された際の乗機。胴体左側面のルイス機銃は30度外向きに装着され、プロペラ回転面を避けて発射された。

(2007/5/7更新)
旧式化した単発偵察・軽爆撃機BE2を代替するために開発された200〜300馬力級複座機。相互の干渉を避けて上下翼の間隔を確保したうえで、前上方視界を改善するために胴体そのものを上に持ち上げたため、下翼と胴体下面の間に隙間のある独特の構成となった。
運動性能はさほどではなかったものの、速度性能は当時のドイツ戦闘機と同等以上であり、前後席が接近していて連携がとりやすいこともあって、対戦闘機戦では前方固定機銃による一撃離脱と後席旋回機銃による追撃排除のコンビネーションで、対爆撃機戦では安定性と航続力とを生かした長時間の追跡と継続射撃で高い戦闘力を発揮した。このため、本来の偵察・砲兵観測・軽攻撃に加え、対空哨戒や夜間迎撃などにも活躍、戦後も連絡機や練習機にまで用途をひろげながら国内外で重宝され、ニュージーランド空軍では1938年まで現役を続けた。標準エンジンのロールスロイス・ファルコンの生産が不足気味だったため、イスパノスイザやサンビーム・アラブなどを積んだ機体も多く、用途に応じた追加装備もよく行われたことから細かなバリエーションは多く、生産終了後も、降着装置の強化や上翼前縁スラットの追加、通信筒回収装置の装備、複操縦装置化といった改装が重ねられた。生産数は試作・先行生産型を含めて1920年までに4799機。
アイコンは、第48飛行中隊のF.2b。
運動性能はさほどではなかったものの、速度性能は当時のドイツ戦闘機と同等以上であり、前後席が接近していて連携がとりやすいこともあって、対戦闘機戦では前方固定機銃による一撃離脱と後席旋回機銃による追撃排除のコンビネーションで、対爆撃機戦では安定性と航続力とを生かした長時間の追跡と継続射撃で高い戦闘力を発揮した。このため、本来の偵察・砲兵観測・軽攻撃に加え、対空哨戒や夜間迎撃などにも活躍、戦後も連絡機や練習機にまで用途をひろげながら国内外で重宝され、ニュージーランド空軍では1938年まで現役を続けた。標準エンジンのロールスロイス・ファルコンの生産が不足気味だったため、イスパノスイザやサンビーム・アラブなどを積んだ機体も多く、用途に応じた追加装備もよく行われたことから細かなバリエーションは多く、生産終了後も、降着装置の強化や上翼前縁スラットの追加、通信筒回収装置の装備、複操縦装置化といった改装が重ねられた。生産数は試作・先行生産型を含めて1920年までに4799機。
アイコンは、第48飛行中隊のF.2b。

(2007/5/22更新)
英国の軍用機開発体制の再生に活躍したジェフリー・デハヴィランドが破損したヴォアザン機を「修復」して製作したBE1複葉機(1911年)の実用発展型。WW1開戦前から量産と部隊配備が進められ、運用経験をもとに居住性、尾翼構成、主翼配置などに順次改良を加えたBE2c(1914年)が決定版となった。緒戦期こそ航続性能・安定性・搭載能力を活かした偵察、砲兵観測、対地攻撃などに活躍し、対飛行船攻撃、対潜哨戒、捜索救難などに使われた機体もあったが、独フォッカー単葉戦闘機が登場すると、低速で運動性の低い本機は多くの損失を出すようになり、改良型も投入されはしたものの、1916年後半には西部戦線から姿を消していった。しかし、エンジン(RAFまたはルノー製空冷V8)の信頼性・整備性の良さ、高い安定性がもたらす離着陸の容易さ、そして改造の余地の大きさゆえに中東、インド方面では重宝され続け、英本土でも斜銃装備の夜間戦闘機や練習機として大戦後半まで現役にあった。量産には王立航空工廠自体はほとんど関与せず、アームストロング=ホイットワース、ブリストル、プロクターなど20社以上を動員して約3500機が生産された。
アイコンは、第13飛行中隊所属のBE2c後期型。パイロットは後席に、偵察員/銃手は前席に座る。
アイコンは、第13飛行中隊所属のBE2c後期型。パイロットは後席に、偵察員/銃手は前席に座る。

(2002/11/17更新)
軽快で前方射撃が可能な単座戦闘機として、エアコDH2と相前後して開発された機体。
空力や細部設計においてはDH2より優れた面もあり、速度や上昇力では同機を若干上回ったが、面積過大で中立保持バネが切れやすい補助翼や面積過小な尾翼のために操縦性やスピン特性が悪く、燃料系統や尾部構造も欠陥を露呈、さらに実戦配備が遅れたこともあって前線での評価は低く、生産数は230機と、DH2の6割にも達しなかった。
アイコンは、1916年夏から第40飛行隊で使用された機体。
空力や細部設計においてはDH2より優れた面もあり、速度や上昇力では同機を若干上回ったが、面積過大で中立保持バネが切れやすい補助翼や面積過小な尾翼のために操縦性やスピン特性が悪く、燃料系統や尾部構造も欠陥を露呈、さらに実戦配備が遅れたこともあって前線での評価は低く、生産数は230機と、DH2の6割にも達しなかった。
アイコンは、1916年夏から第40飛行隊で使用された機体。
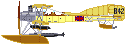
(2003/2/20更新)
1910年以来ショート社が開発し続けてきた一連の水上機の完成形。早くも開発・テストの段階で他社機を退けて魚雷発射母機に選定され、生産原型機1機と量産1・2号機が水上機母艦リヴィエラ及びベン・マイ・クリーに搭載されて実験出撃している。この航海中の1915年8月12日、エドモンド中佐による史上初の航空雷撃命中(トルコの5000トン級輸送船)が記録されたが、これは潜水艦との共同戦果であり、航空雷撃のみによる初の戦果は、同月17日のエドモンド中佐による船舶炎上とデイカー中佐によるタグボート撃沈だとされている。
本機は魚雷を積むには絶対的にアンダーパワーであり、雷装時には偵察員なしでも45分ぶんの燃料を積むのがやっとで、しかも高度460m以上には上がれなかったという。よって実戦で雷装することはほとんどなく、小型爆弾による爆撃や偵察(ユトランド海戦での接敵成功が有名)を主な任務とした。
アイコンは、エドモンド中佐搭乗の量産2号機。本格量産型に比べてフロートが大きいことに注意。
本機は魚雷を積むには絶対的にアンダーパワーであり、雷装時には偵察員なしでも45分ぶんの燃料を積むのがやっとで、しかも高度460m以上には上がれなかったという。よって実戦で雷装することはほとんどなく、小型爆弾による爆撃や偵察(ユトランド海戦での接敵成功が有名)を主な任務とした。
アイコンは、エドモンド中佐搭乗の量産2号機。本格量産型に比べてフロートが大きいことに注意。

(2007/4/12更新)
1914年のシュナイダー杯レース優勝機である「タブロイド」水上機の軍用改装型。前期型を「シュナイダー」と称したが、エンジン装着法の変更、撓み翼式から補助翼式への変更、翼面積の拡大などの改修が時差的に行われたことから、後期型「ベイビー」との区分は明確ではない。海軍が単座小型水上機の運用方針を固めきれなかったことや、陸上機の生産に追われていたソッピース社から他社への転換生産の立ち上がりがもたついたこと、さらには操縦性・水上安定性の改善や搭載量増大に見合う離水性能向上のための改修が相次いだことから実戦化は遅々として進まなかった。部隊配備されてからも、武装方式の迷走や飛行船迎撃に必要な高空性能の不足などから一時は存在意義を疑われさえもした。しかし、WW1後半は艦隊防空、洋上・対潜・対空哨戒、捜索救難などに活躍し、オランダ、フランス、イタリア、ノルウェイ、日本などに輸出されて一部は1930年まで稼動状態を維持するなど、その出自にふさわしい経歴を飾っている。系列全体の生産数は、ブラックバーン、フェアリー及びパーナルでの生産分を含めて602機。パーナル社製造機の中には、フェアリーで設計・試作された可変カンバー式の主翼を持つものもあった。
アイコンは、1917年後半にエーゲ海方面に展開し、後にギリシャ海軍に譲渡されたブラックバーン製の機体。機首に同調式のルイス機銃を装備している。

(2007/5/22更新)
英海軍向けの高速複座多用途機として開発された機体。基本的には一張間の複葉機であるが、着陸張線が中央支柱からではなく、その外側に独立して設けられた斜め支柱(前から見ると中央支柱とあわせてW字を描く)から張られていることから、「一張間半」という独特の名称を持つ。複座機としては軽量コンパクトで運動性が高く、また、初期型を除いて同調式の前方機銃を装備したことから、折から隆盛を誇っていたフォッカー単葉機に対抗できる制空戦闘機として英陸海両軍で活躍した。独アルバトロス機に対抗するには性能不足だったため、制空戦闘機としての寿命は1916年後半までに尽きてしまったが、その後も複座偵察機、後席をつぶして爆弾倉とした高速爆撃機、前席をつぶして斜銃を装備した本土防空用夜戦などとして活用され続けた。その多任務適合性ゆえに、英国内ではソッピース以外にもモーガン、ウエストランド等を含めて約1500機が、フランスでもダラック、アンリオ、リオレ・エ・オリヴィエ等で約4500機が生産され、ベルギー、ロシア等には制式兵器としてまとまった数が輸出され、アメリカ海軍は戦艦搭載機として使用、日本も研究用に少数機を導入するなど、この世代の複座単発機のスタンダードともいえる存在であった。
アイコンは、1917年春ごろ、第43飛行中隊に配備されていた機体。
アイコンは、1917年春ごろ、第43飛行中隊に配備されていた機体。

(2002/11/18更新)
WW1末期、各国とも戦闘機はドッグファイト志向の回転式空冷エンジン搭載機と一撃離脱志向の液冷エンジン搭載機に分化する傾向があったが、イギリスにおける前者の代表が本機である。機銃とコクピットを極端に前進させ、もともとコンパクトな機体の重心付近に重量を集中、これを上下両翼に設けた大面積の補助翼で振り回すことで驚異的な運動性能を得た。その代償として、殊に離着陸時にプロペラ反力の影響を受けやすく、さらに燃料消費にともなう重心移動が大きかったため、操縦性は非常に神経質で事故も多かった。また、ドッグファイト中心の戦法では被弾する確率も高く、戦果も損失もWW1英国戦闘機中最大の機種となっている。
標準的な武装は、機首上面のヴィッカース同調式機銃2丁だが、ヴィッカース機銃を1丁に減じて主翼上装備のルイス機銃1丁と組み合わせた海軍型や、同調式機銃を廃して主翼上に斜め上向きの連装式ルイス機銃を装備した防空戦闘型もある。
アイコンは、海軍第13飛行隊のL.H.スラッターの乗機(搭乗時の階級は不詳)。
標準的な武装は、機首上面のヴィッカース同調式機銃2丁だが、ヴィッカース機銃を1丁に減じて主翼上装備のルイス機銃1丁と組み合わせた海軍型や、同調式機銃を廃して主翼上に斜め上向きの連装式ルイス機銃を装備した防空戦闘型もある。
アイコンは、海軍第13飛行隊のL.H.スラッターの乗機(搭乗時の階級は不詳)。

(2005/8/1更新)
1918年4月21日、英空軍第209飛行隊のブラウン中尉は、独陸軍JG1との空戦中、僚機を追撃していた敵フォッカーDr.Iを射撃し、墜落させた。このとき戦死した独軍パイロットこそ、80機撃墜のスーパーエース、マンフレート・フォン・リヒトホーフェンその人であった。
この撃墜劇については、ブラウン中尉の戦果だとする説と地上に展開していたオーストラリア軍の対空射撃によるものだとする説との論争がいまだに続いているが、彼が最終撃墜数10機のエースにして優秀な編隊長であり、この日の戦闘を含む功績により殊勲十字章(DFC)を授与された実績は揺らぐものではない。
カナダ生まれのブラウンは、質実な性格の持ち主であり、近代的軍隊の一員としての教育を受けたこともあって、戦果を主張はしても必要以上に英雄扱いされることを好まず、リヒトホーフェン撃墜についても、自ら進んで多くを語ろうとはしなかったという。
この撃墜劇については、ブラウン中尉の戦果だとする説と地上に展開していたオーストラリア軍の対空射撃によるものだとする説との論争がいまだに続いているが、彼が最終撃墜数10機のエースにして優秀な編隊長であり、この日の戦闘を含む功績により殊勲十字章(DFC)を授与された実績は揺らぐものではない。
カナダ生まれのブラウンは、質実な性格の持ち主であり、近代的軍隊の一員としての教育を受けたこともあって、戦果を主張はしても必要以上に英雄扱いされることを好まず、リヒトホーフェン撃墜についても、自ら進んで多くを語ろうとはしなかったという。

(2003/4/13更新)
(2003/8/16更新)
フランス軍向けに開発していたB.1攻撃機の設計を流用して開発された雷撃機。ソッピース社の生産能力がキャメル戦闘機等のために手一杯だったこともあり、海軍と縁の深いブラックバーン社で量産されることになった。しかし、装備エンジンが二転三転(イスパノスイザ→サンビーム・アラブ→ウーズレイ・ヴァイパー)し、量産に向けた機体構造の見直しにも手間取ったことから生産は進まず、運用面でもフューリアス、アーガス両空母の離着艦設備の完成や乗員の訓練が遅れたため、「雷撃機100機を擁する空母機動部隊を以て停泊中のドイツ高海艦隊を殲滅する」という作戦計画は幻に終わった。戦後もエンジンをロールスロイス・ファルコンに強化する等の改良が行われたが、単座機ゆえの航法・通信・防御能力の不足はいかんともしがたく、航空雷撃の研究機材としての扱いに終わった。
アイコンは、1918年生産のサンビームエンジン搭載機。
アイコンは、1918年生産のサンビームエンジン搭載機。

(2003/7/27更新)
(2003/8/15更新)
(2007/4/11更新)
1916年、フォッカーE.IIIの台頭によるドイツの航空優勢に対抗するため、英陸海軍では対空戦闘を重視した航空戦力の編成を進めていた。しかし、イギリス製戦闘機は独仏に比べて質量ともに不十分な状況であり、中には装備する機体のないまま戦線に送られる部隊さえあった。この空白を埋めたのが、モラン=ソルニエ・タイプN、スパッド7、ニューポール11〜17の各機種である。特にニューポール17は、その軽快な機動性でパイロットに愛されたばかりでなく、ソッピース・キャメルやS.E.5といった高性能な国産機が充足した1917年後半においても一部で使用が続くほどの有効性を示した。イギリス軍が使用した機体では、フランス軍よりも機銃同調装置の装備が遅れており、機銃を主翼上に装備したものの割合が高いようである。
アイコンは、カナダ出身のビリー=ビショップ(最終撃墜数72)の乗機。
アイコンは、カナダ出身のビリー=ビショップ(最終撃墜数72)の乗機。

(2006/7/10更新)
WW1初期のフランス航空戦力の一翼を担った多用途機。1911年のAbis型以来の、エンジンとコクピットからなる中央胴体に尾橇兼用の梯子状フレーム双胴の尾部を組み合わせた原始的ともいえる構成で、しかも偵察員手持ちのライフル以外に武装のない機体ではあったが、操縦が容易で実用性にすぐれ、量産体制も整っていたことから、開戦直後に大量発注がなされ、偵察、砲兵観測、洋上哨戒、操縦練習などに使われた。操縦席は後席だが、操縦系統を前席に移したり、複操縦装置化した機体もある。
生産数は、ポテ、ブレリオ、ドペルデュサン、航空工廠での生産分を含めてフランス国内だけで2450機に達し、イギリス、ポルトガル、イタリアでもライセンス生産された。また、ロシア、アメリカ、チェコスロヴァキア、ルーマニア、ベルギー、フィンランド、コロンビア、中国等にも輸出され、各国軍事航空の確立に貢献している。装備エンジンは、アイコンのグノーム回転式のほかにアンザニ固定式星型、ルノーV8などがある。
生産数は、ポテ、ブレリオ、ドペルデュサン、航空工廠での生産分を含めてフランス国内だけで2450機に達し、イギリス、ポルトガル、イタリアでもライセンス生産された。また、ロシア、アメリカ、チェコスロヴァキア、ルーマニア、ベルギー、フィンランド、コロンビア、中国等にも輸出され、各国軍事航空の確立に貢献している。装備エンジンは、アイコンのグノーム回転式のほかにアンザニ固定式星型、ルノーV8などがある。

(2003/7/27更新)
(2007/4/11更新)
輸出用戦闘機HD.1のフランス海軍型。水上戦闘機として130機が発注され、海軍基地の防空などに従事した。エンジンをクレルジェ130馬力に強化したり車輪式降着装置に換装したりした機体も多く、戦艦パリ主砲塔上の特設プラットフォームからの離艦テストや空母ベアルンからの離着艦テストに成功する等、フランス海軍航空史上に足跡を残した。イタリア海軍でも少数が対潜哨戒などに使われている。
アイコンは、仏海軍第3次発注分の機体で、大型の垂直尾翼を装備している。
アイコンは、仏海軍第3次発注分の機体で、大型の垂直尾翼を装備している。

(2004/1/30更新)
タイプG軽飛行機をパラソル翼化して安定性と下方視界を改善した機体。もともとは偵察・対地攻撃を主任務とする複座多用途機として開発され、フランス陸軍で採用されたほか、トルコ、ロシア等にも輸出されている。フランスでの生産数は約600機だが、ロシアでのライセンス生産やドイツでのコピー生産を含めると1100機程度になる。
1914年末、モラン=ソルニエ社のテストパイロットでもあったローラン=ガローは、プロペラ回転圏内に前方発射式固定機銃を装備して機体の機動により照準する空中戦術(これ自体は彼の発想ではない)を実現するため、整備員ジュール=ヒューの協力を得て金属製跳弾板付きプロペラを開発、実験を重ねた末、1915年4月1日から18日にかけて5機のドイツ機を撃墜することに成功した。これによりフォーマットを確立された「戦闘機」は、同盟国側のみならず、撃墜した彼の乗機を検分したドイツ側においても急速に広まっていくこととなった。
アイコンは、ガローが搭乗した初期型、すなわち「世界最初の戦闘機」である。
1914年末、モラン=ソルニエ社のテストパイロットでもあったローラン=ガローは、プロペラ回転圏内に前方発射式固定機銃を装備して機体の機動により照準する空中戦術(これ自体は彼の発想ではない)を実現するため、整備員ジュール=ヒューの協力を得て金属製跳弾板付きプロペラを開発、実験を重ねた末、1915年4月1日から18日にかけて5機のドイツ機を撃墜することに成功した。これによりフォーマットを確立された「戦闘機」は、同盟国側のみならず、撃墜した彼の乗機を検分したドイツ側においても急速に広まっていくこととなった。
アイコンは、ガローが搭乗した初期型、すなわち「世界最初の戦闘機」である。

(2004/1/15更新)
もともとは1914年6月にウィーンのアスペルンで開かれた飛行大会に出場するために既存のタイプG/Hに空力的洗練を加えて作られた機体であったが、この大会で総合2位の好成績をおさめたこともあり、同社のタイプLパラソル翼機に続いて戦闘機化されることとなった。
世界で初めて前方発射式固定機銃を標準装備したが、弾薬の品質が不均一で機銃が同調装置の管制どおりに作動しないおそれがあったことから、非同調式のオチキス機銃(保弾板式!)を装備、弾丸がプロペラを破壊しないよう、ブレード裏面にV字型の金属製跳弾板を装備した。
羽布張りながら円形断面の流線形に成型された胴体の形から「モノコック」と称されたほどの空力的洗練とレーサー上がりのコンパクトな設計のおかげで、わずか80馬力のエンジン出力と高速ロールに不利な撓み翼式操縦系ながらも、フォッカーE.IIIをわずかに上回る速度・機動性能を発揮した。しかし、下方視界の悪さや着陸速度過大、薄翼単葉機特有の強度不足等のため、ニューポール、スパッド両戦闘機の出現とともに姿を消し、生産数も翼面積拡大・高出力型のタイプI/Vを含めて65機(他にロシア発注分20機?)にとどまっている。
アイコンは、英陸軍航空隊に供与されて第60飛行隊のベイエット中尉の乗機となった機体。
世界で初めて前方発射式固定機銃を標準装備したが、弾薬の品質が不均一で機銃が同調装置の管制どおりに作動しないおそれがあったことから、非同調式のオチキス機銃(保弾板式!)を装備、弾丸がプロペラを破壊しないよう、ブレード裏面にV字型の金属製跳弾板を装備した。
羽布張りながら円形断面の流線形に成型された胴体の形から「モノコック」と称されたほどの空力的洗練とレーサー上がりのコンパクトな設計のおかげで、わずか80馬力のエンジン出力と高速ロールに不利な撓み翼式操縦系ながらも、フォッカーE.IIIをわずかに上回る速度・機動性能を発揮した。しかし、下方視界の悪さや着陸速度過大、薄翼単葉機特有の強度不足等のため、ニューポール、スパッド両戦闘機の出現とともに姿を消し、生産数も翼面積拡大・高出力型のタイプI/Vを含めて65機(他にロシア発注分20機?)にとどまっている。
アイコンは、英陸軍航空隊に供与されて第60飛行隊のベイエット中尉の乗機となった機体。

(2007/4/12更新)
複座偵察機を原型としていたために設計に不満足な部分のあった10、11両型の後継機として、スパッドS.7とともに独フォッカー単葉機への最終回答として開発された、フランス初の本格的単発単座戦闘機。以前の型より拡大(約13m2→約15m2)された翼面積と自重375kgという軽量構造とがもたらす運動性と加速力によって、連合軍による制空権奪取の立役者となった。当初の武装は上翼中央やぐら上のルイス機銃1丁だったが、後に機首上面にヴィッカース同調式機銃を装備することもできるようになり、これらを組み合わせて1〜2丁搭載した。フランス軍のほか、イギリス、イタリア、ロシア、ベルギー等にも供与され、エンジンや胴体断面形、操縦翼面等に順次改良を加えた21〜27各型へと発展しながら大戦を戦い抜いた。しかし、スパッド戦闘機に比べて低速で、単桁式の下翼(迎角調整式)の捻り強度不足や回転式空冷エンジンのジャイロ効果のために空戦機動に細心の注意が必要だったことから、しだいにその勢力は小さくなっていった。
アイコンは、フランス陸軍第1位のエース、ルネ=フォンク(最終撃墜数75)の乗機。
アイコンは、フランス陸軍第1位のエース、ルネ=フォンク(最終撃墜数75)の乗機。

(2003/12/17更新)
(2003/12/21更新)
制空戦闘機として成功をおさめた17型の改良型。エンジンを強化したほか、胴体断面を四角形から円形にし、垂直尾翼を木製の曲線形状に改める(先行生産型24bisは17型のまま)等の空力的改善を施した。
しかし、機体サイズに対してエンジンの重量と出力が過大なため操縦が難しく、部隊配備初期に昇降舵シーリング不良による事故もあったこと等から、スパッドS.13の地位を脅かすどころか17型の更新用機材としても評価されなかったため、戦闘機としてはあまり使用されず、フランス軍では主に低出力エンジンに換装した練習機型を使用した。
しかし、機体サイズに対してエンジンの重量と出力が過大なため操縦が難しく、部隊配備初期に昇降舵シーリング不良による事故もあったこと等から、スパッドS.13の地位を脅かすどころか17型の更新用機材としても評価されなかったため、戦闘機としてはあまり使用されず、フランス軍では主に低出力エンジンに換装した練習機型を使用した。

(2004/4/8更新)
1917年5月の航空技術局仕様書に応えて開発された世界初の300馬力級戦闘機。会社名と設計者ギュスターヴ=ドラージュの名をとってNi.D-29とも呼ばれる。1918年6月からのSPAD51等との比較選考に勝利し、8月には増加試作にまで進んだが、試作機の事故やその修理に伴う改修のために第一次大戦には間に合わなかった。しかし、その高性能、特に運動性の高さゆえに戦後の機種削減を生き残り、1920年代を通して仏陸軍主力戦闘機の座にあった。フランス陸軍向けの生産数は700機程度だが、ライセンス生産もイタリア(175機)・ベルギー(87機)・日本(654機)と数多く行われており、この3か国及びスウェーデン、スペイン、タイへの輸出を含めれば1500機を軽く超えるベストセラー機である。
実戦参加は仏領モロッコの反乱鎮圧、日中戦争緒戦、タイ防空戦等の小規模なものにとどまるが、エアレーサーや速度記録機、高高度実験機のベース機としても成果を挙げ、戦間期フランス航空界を代表する機体のひとつとなった。
アイコンは、1920年代前半の第81飛行隊所属機。
実戦参加は仏領モロッコの反乱鎮圧、日中戦争緒戦、タイ防空戦等の小規模なものにとどまるが、エアレーサーや速度記録機、高高度実験機のベース機としても成果を挙げ、戦間期フランス航空界を代表する機体のひとつとなった。
アイコンは、1920年代前半の第81飛行隊所属機。

(2006/5/30更新)
WW1後期フランス製偵察・軽爆撃機の傑作。前部胴体フレームと中央翼支柱を一体構造とするなどした強固な機体構造に、クランク上のギア機構でコンロッドとクランクの位置関係を補正して各気筒の運転条件を均等化するカントン・ウネ機構を持つ高出力・低振動・高信頼性のエンジンを組み合わせた、当時としては先進的な設計であった。
最高速度こそ186km/hにとどまるが、良好な高高度性能、ドイツ戦闘機の追撃をかわしうる運動性・加速性、癖のない操縦性と長時間飛行向きの安定性、自動防漏タンクの装備など、任務達成率と生存性に優れた機体であった。このため、より高出力・大登載量のブレゲー14A2と競合しながらも3200機を生産、フランス陸軍のほか、米陸軍遠征軍、チェコスロヴァキア、ポーランド等でも使われるベストセラーとなった。
アイコンは、Sal.28(第28サルムソン飛行隊)の使用機。
最高速度こそ186km/hにとどまるが、良好な高高度性能、ドイツ戦闘機の追撃をかわしうる運動性・加速性、癖のない操縦性と長時間飛行向きの安定性、自動防漏タンクの装備など、任務達成率と生存性に優れた機体であった。このため、より高出力・大登載量のブレゲー14A2と競合しながらも3200機を生産、フランス陸軍のほか、米陸軍遠征軍、チェコスロヴァキア、ポーランド等でも使われるベストセラーとなった。
アイコンは、Sal.28(第28サルムソン飛行隊)の使用機。

(2002/9/22更新)
(2003/8/16更新)
上翼と主脚から支柱を介してプロペラ前方にある銃座を支え、そこから前方に機銃(上下可動式)を撃つという、戦闘機カテゴリ自体の模索期に咲いた徒花。
銃座の陰になったプロペラの効率低下(それでも80馬力のルローンで152km/hを発揮)やコクピットからの視界の悪さのためパイロットには甚だ不評で、フランス軍向け42機と帝政ロシア軍向け57機で生産を終了している。
しかし、主翼および胴体の構造は後のスパッド高速戦闘機シリーズの基礎となる洗練されたものであり、技術史的には重要な機体である。
なお、エンジンをルローン9J(110馬力)、最高速度154km/hとする資料もある。
銃座の陰になったプロペラの効率低下(それでも80馬力のルローンで152km/hを発揮)やコクピットからの視界の悪さのためパイロットには甚だ不評で、フランス軍向け42機と帝政ロシア軍向け57機で生産を終了している。
しかし、主翼および胴体の構造は後のスパッド高速戦闘機シリーズの基礎となる洗練されたものであり、技術史的には重要な機体である。
なお、エンジンをルローン9J(110馬力)、最高速度154km/hとする資料もある。

(2004/2/1更新)
(2007/4/10更新)
ニューポール17と並ぶフランス初の本格的戦闘機として作られた機体。マルク=ビルキグトの手になる軽量高出力のイスパノスイザ水冷V8エンジンにドペルデュサン競速機の設計者ルイ=ベシュローの空力デザインを組み合わせることで、実用戦闘機としては世界で始めて200km/h台に到達した。出力重量比と構造強度の高さがもたらす加速・上昇・急降下性能を生かした一撃離脱戦法を得意としたが、低いロール率や失速特性の悪さ、エンジン全開時の直進性の悪さもあって、総合評価でニューポールを引き離すには至らなかった。
しかし、フォンク(撃墜数75)、ギヌメール(同54)、ナンジェッセ(同45)といった大エースたちの愛機として名を馳せ、特に「こうのとり部隊」こと第3飛行大隊での活躍は航空戦史上の伝説にまでなっている。また、イギリス、アメリカ、イタリア、ベルギー等にも輸出され、各国の戦闘機戦力の確立に貢献した。
アイコンは、第3飛行大隊第26飛行中隊の滋野清武大尉(撃墜数5(7?))乗機「わかどり」号。胴体には部隊標準のこうのとりではなく、丹頂鶴が描かれている。
しかし、フォンク(撃墜数75)、ギヌメール(同54)、ナンジェッセ(同45)といった大エースたちの愛機として名を馳せ、特に「こうのとり部隊」こと第3飛行大隊での活躍は航空戦史上の伝説にまでなっている。また、イギリス、アメリカ、イタリア、ベルギー等にも輸出され、各国の戦闘機戦力の確立に貢献した。
アイコンは、第3飛行大隊第26飛行中隊の滋野清武大尉(撃墜数5(7?))乗機「わかどり」号。胴体には部隊標準のこうのとりではなく、丹頂鶴が描かれている。

(2002/10/6更新)
(2007/4/10更新)
時の大エース、ジョルジュ=ギヌメールの発案により開発された「大火力戦闘機」。スイス人技師マルク=ビルキグトが設計したモーターカノン(陸戦用37mm砲を短砲身化したもの)を装備、その砲尾が操縦席内にはみ出したため、通常の操縦桿ではなく、逆U字型のピッチ操縦バーに操縦輪、という大型機のような操縦装置を持つ。また、副武装として機首上面に7.7mmヴィッカース同調機銃1丁を備える。
1917年7月のギヌメールによる運用テストでその性能を立証して制式採用となったが、イスパノスイザ220馬力エンジンの量産が砲身貫通部となる減速ギアの強度問題により遅延し、また、37mm砲の照準・再装填の難しさや発射ガスのコクピットへの充満、発射振動によるエンジン故障、機首下げ傾向といった問題を抱えていたため、実戦配備された機体の稼働率も低く、終戦時点での稼動機はたった12機だったともいう。
それでも、高速(220km/h@海面高度)と上昇・急降下性能を生かして敵機に肉薄、これを一撃で粉砕するという戦法には適しており、ルネ=フォンクが本機搭乗時に11機撃墜の戦果を挙げる等、エース専用機として一定の成績を残した。
アイコンはジョルジュ=フェリクス=メイドン(最終撃墜数41機)の乗機。
1917年7月のギヌメールによる運用テストでその性能を立証して制式採用となったが、イスパノスイザ220馬力エンジンの量産が砲身貫通部となる減速ギアの強度問題により遅延し、また、37mm砲の照準・再装填の難しさや発射ガスのコクピットへの充満、発射振動によるエンジン故障、機首下げ傾向といった問題を抱えていたため、実戦配備された機体の稼働率も低く、終戦時点での稼動機はたった12機だったともいう。
それでも、高速(220km/h@海面高度)と上昇・急降下性能を生かして敵機に肉薄、これを一撃で粉砕するという戦法には適しており、ルネ=フォンクが本機搭乗時に11機撃墜の戦果を挙げる等、エース専用機として一定の成績を残した。
アイコンはジョルジュ=フェリクス=メイドン(最終撃墜数41機)の乗機。

(2005/8/1更新)
フォッカーEシリーズに続くドイツ軍主力戦闘機として、主な想定目標である偵察・爆撃機の性能向上に対応するとともに、ニューポール11、エアコDH.2等の英仏戦闘機に対抗できる空戦性能をも求められて開発された機体。エンジン出力の割に機体重量がややかさんだため、飛行性能面で抜きん出たものはなかったが、重量増を忍んで高初速・高発射速度のMG08/15機銃を2丁装備した強武装と素直な操縦性のおかげで総合的な戦闘力は高かった。木製モノコック構造の紡錘形胴体は、空力性能が良いだけでなく、内部張線の調整なしに胴体の形状と強度を保てるため、整備性も良かったという。
試作・先行量産型D.I(生産数62)に続き、主翼取付方式を変更して前方視界を改善し、ラジエターを胴体側面突出式から主翼中央上面埋込式に変更したD.IIが生産され、ともに1916年秋から本格的な配備が始まっている。生産数はアルバトロス社製200機のほか LVG社製75機。
アイコンは、第2戦闘中隊のマンフレート・フォン・リヒトホーフェンが初めての公認撃墜を記録した際の乗機。D.Iとして発注されて1916年9月に配備されたD.II初期型なので、ラジエターはまだ胴体側面に装備されている。
試作・先行量産型D.I(生産数62)に続き、主翼取付方式を変更して前方視界を改善し、ラジエターを胴体側面突出式から主翼中央上面埋込式に変更したD.IIが生産され、ともに1916年秋から本格的な配備が始まっている。生産数はアルバトロス社製200機のほか LVG社製75機。
アイコンは、第2戦闘中隊のマンフレート・フォン・リヒトホーフェンが初めての公認撃墜を記録した際の乗機。D.Iとして発注されて1916年9月に配備されたD.II初期型なので、ラジエターはまだ胴体側面に装備されている。

(2005/8/1更新)
D.IIの飛行性能、特に運動性を改善するため、仏ニューポール戦闘機に範をとった一葉半形式の主翼に改めた機体。翼間支柱がV型となっていることからわかるように、下翼は翼弦の狭い単桁式である。この新主翼により、運動性、特に上昇力と横転性能が向上したが、ニューポール機の弱点である下翼の捻り強度不足も受け継いでしまい、高速急降下や高G機動時に空中分解しやすいという持病を抱えることになってしまった。生産数は1340機。
本機は、その性能ばかりでなく、専門の飛行隊(Jasta:戦闘中隊)の創設による空対空専門戦力の集中運用化の波に乗ったことによって圧倒的な戦闘力を発揮し、先行型D.IIとともに1917年春の「血まみれの4月」と呼ばれる航空攻勢の主役となった。しかし、英仏がスパッド13、S.E.5等を充足させ、空対空戦力の編成も改めてきた1917年後半になると急速に優位を失っていった。
アイコンは、1917年中頃にJasta50で使用されていた機体。後のD.Vと共通する丸い輪郭の大型方向舵は、O.A.W(東ドイツアルバトロス工場)生産機の特徴である。
本機は、その性能ばかりでなく、専門の飛行隊(Jasta:戦闘中隊)の創設による空対空専門戦力の集中運用化の波に乗ったことによって圧倒的な戦闘力を発揮し、先行型D.IIとともに1917年春の「血まみれの4月」と呼ばれる航空攻勢の主役となった。しかし、英仏がスパッド13、S.E.5等を充足させ、空対空戦力の編成も改めてきた1917年後半になると急速に優位を失っていった。
アイコンは、1917年中頃にJasta50で使用されていた機体。後のD.Vと共通する丸い輪郭の大型方向舵は、O.A.W(東ドイツアルバトロス工場)生産機の特徴である。

(2005/8/1更新)
性能的優位を失いつつあったD.IIIの改良型として、エンジンを強化(160馬力 →180馬力)するとともに、主翼取付方法を変更し、側面が平面だった胴体断面を楕円断面に改める等の改設計を行った機体。機体重量が増加したため、性能的には上昇力と速度が若干向上したにとどまったが、素直な操縦性は失われず、すでに量産体制も整っていたことから、1917年初夏から終戦まで他社の新型機と併用されてドイツ戦闘機戦力の屋台骨を支え続けた。生産数はD.Vが900機と、不評だった操縦系統をD.IIIの方式に戻し、後方視界を妨げていたヘッドレストを廃止する等した改良型D.Vaが1612機の計2512機。むろんWW1ドイツ機中最多である。
アイコンは、Jasta40のヘルムート=ディルタイ(最終撃墜数7)乗機D.Va。
アイコンは、Jasta40のヘルムート=ディルタイ(最終撃墜数7)乗機D.Va。

(2002/9/28更新)
全幅6.2m、全長4.5mという超小型の機体にメルセデス100馬力エンジンを搭載、190km/hの快速を発揮したが、視界の悪さと着陸操縦の困難から制式採用されずに終わってしまった。
胴体側面形は涙滴形だが、正面から見ると直6エンジンとパイロットの肩幅ぎりぎりしかない角丸長方形をしている。
胴体側面形は涙滴形だが、正面から見ると直6エンジンとパイロットの肩幅ぎりぎりしかない角丸長方形をしている。

(2002/11/25更新)
「フォッカーの懲罰」と称されたドイツ陸軍航空隊大攻勢の主役。前方固定機銃のアイデアと機体の基本構造こそ仏モラン=ソルニエから拝借したものの、単なるコピーではなく、機銃同調装置(発明自体は1913年)を採用し、鋼管溶接工法によって量産性を向上させることで、兵器としての完成度を高めた。
それまでの「戦闘機」が既存の偵察機やレーサーに機銃を積んだだけのようなものだったのに対し、E.IIIは燃料タンクを操縦席前方から後方に移して弾薬収納スペースを確保し、翼面積を増して運動性を改善する等「システムとしての戦闘機」を志向して作られた世界初のものだったといってよい。
しかし、撓み翼式操縦方式の宿命として、特に高速時の横操縦が重く、翼操作のための複雑なワイヤーや支柱が空気抵抗になって速度性能もいまいちだったため、英仏機が前方固定機銃を標準化させた1916年中盤以降は優位を失っていった。
生産数は、輸出分を含めて約300機。
それまでの「戦闘機」が既存の偵察機やレーサーに機銃を積んだだけのようなものだったのに対し、E.IIIは燃料タンクを操縦席前方から後方に移して弾薬収納スペースを確保し、翼面積を増して運動性を改善する等「システムとしての戦闘機」を志向して作られた世界初のものだったといってよい。
しかし、撓み翼式操縦方式の宿命として、特に高速時の横操縦が重く、翼操作のための複雑なワイヤーや支柱が空気抵抗になって速度性能もいまいちだったため、英仏機が前方固定機銃を標準化させた1916年中盤以降は優位を失っていった。
生産数は、輸出分を含めて約300機。

(2005/4/28更新)
イギリスのソッピース・トリプレーンに対抗して試作された各社三葉戦闘機の中で、唯一ドイツ軍制式兵器となった機体。翼幅と翼弦長を抑えて横転・縦操縦性を保ったまま翼面積を増やして低翼面荷重を実現する三葉機本来の特性に加え、箱型構造の強固な主桁と大きな前縁半径を持つ厚翼を採用することで、翼間支柱・張線の省略による整備性の高さと、失速特性の良さからくる急角度上昇・旋回性能をも獲得した。なお、主翼間の支柱は防振と三葉の荷重変形の均等化のためのものであり、強度上の意味はほとんどない。
かのリヒトホーフェンをして「猿の如く昇り、悪魔の如く舞う」と言わしめたほどの格闘戦性能を誇った本機だが、主翼防湿加工不良による空中分解癖の改修のために実戦配備が遅れ、また、エンジンの出力不足と空気抵抗過大からくる鈍足ゆえ優速の敵機に囲まれたときの戦闘離脱が困難(フォス、リヒトホーフェン両エース戦死の遠因でもある)なことから主力戦闘機にはなりえず、生産数は約320機にとどまり、練習機とされた機体も多い。しかし、熟練パイロットの中には終戦近くまで本機での出撃を続けて相応の戦果を挙げた者もいる。
アイコンは、第2戦闘中隊のフリードリッヒ=ケンプ少尉機。
かのリヒトホーフェンをして「猿の如く昇り、悪魔の如く舞う」と言わしめたほどの格闘戦性能を誇った本機だが、主翼防湿加工不良による空中分解癖の改修のために実戦配備が遅れ、また、エンジンの出力不足と空気抵抗過大からくる鈍足ゆえ優速の敵機に囲まれたときの戦闘離脱が困難(フォス、リヒトホーフェン両エース戦死の遠因でもある)なことから主力戦闘機にはなりえず、生産数は約320機にとどまり、練習機とされた機体も多い。しかし、熟練パイロットの中には終戦近くまで本機での出撃を続けて相応の戦果を挙げた者もいる。
アイコンは、第2戦闘中隊のフリードリッヒ=ケンプ少尉機。

(2005/4/28更新)
WW1最高のエース、マンフレート・フォン・リヒトホーフェン(撃墜数80)最後の乗機。羽布を全て絹張りにして空気抵抗を低減していたとか、撃墜した仏ニューポール機のエンジンに換装して出力と信頼性を改善していたとか伝えられているが、前者は判明している絹張り実験機の配備先から否定されており、後者はヴェルナー=フォス(撃墜数48)乗機等との混同と思われる。しかし、リヒトホーフェンがあえて鈍足かつ目立つ塗装の本機に乗って敵を引き付け、高速のアルバトロス機に乗った部下に奇襲と戦闘離脱の機会を与えていたというのは事実のようである。
アイコンは胴体全面と各翼上面を赤とする説に従ったが、中央胴体と中・下翼上面は正規塗色のオリーブグリーンのままだったという説も有力である。
アイコンは胴体全面と各翼上面を赤とする説に従ったが、中央胴体と中・下翼上面は正規塗色のオリーブグリーンのままだったという説も有力である。

(2003/3/11更新)
新鋭フォッカー D.VIIの保険として作られた機体で、Dr.I三葉機の胴体にD.VIIの主翼を付けたハイブリッド機である。
D.VIには試作時の長胴型と量産時の短胴型があり、後者の胴体はDr.Iのものを一部改造したもの(全長が同じ、エンジンも同じオーバーウルゼルUr.II)らしい。尾翼は長短両型ともDr.Iの流用。主翼はD.VIIと共通の設計だが、左右それぞれリブ2枚分短縮したものになっている。
本機はスペック上の性能ではD.VIIを上回ったものの、試作時のエンジン(Ur.IIIまたはジーメンス・ハルスケSh.III)はおろか量産型のUr.IIですら信頼性に問題があり、実戦に出すべきではないと判断されて、D.VIIの成功が確実になった時点でキャンセル、わずか59機の生産にとどまった。
エンジンはオーバーウルゼル星型回転式108hp、最高速度197Km/h、武装MG08 7.92mm機銃× 2。
D.VIには試作時の長胴型と量産時の短胴型があり、後者の胴体はDr.Iのものを一部改造したもの(全長が同じ、エンジンも同じオーバーウルゼルUr.II)らしい。尾翼は長短両型ともDr.Iの流用。主翼はD.VIIと共通の設計だが、左右それぞれリブ2枚分短縮したものになっている。
本機はスペック上の性能ではD.VIIを上回ったものの、試作時のエンジン(Ur.IIIまたはジーメンス・ハルスケSh.III)はおろか量産型のUr.IIですら信頼性に問題があり、実戦に出すべきではないと判断されて、D.VIIの成功が確実になった時点でキャンセル、わずか59機の生産にとどまった。
エンジンはオーバーウルゼル星型回転式108hp、最高速度197Km/h、武装MG08 7.92mm機銃× 2。
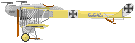
(2004/10/11更新)
(2007/4/10更新)
1914年3月にドイツ政府が策定した軍用飛行機仕様のうち第3類に対応して軍民共同開発されたフリーデル=ウルジヌス3座双発機をゴータ社が量産化した機体。胴体を高い位置に置いた構成は、速度変化に伴う空気抵抗中心の上下動を緩和し、左右両エンジンを接近させて片発飛行時の方向安定を高め、さらに機首銃座からの全周射界を確保するためのものである。乗員区画は合計150kgに及ぶクローム=ニッケル鋼製装甲板で守られ、機首ターレットには7.92mm機銃のほか、20mmベッカー砲やラインメタル37mm砲の装備も可能であった。
運動性の低さや転覆時の危険性、胴体尾部の強度不足等の問題から生産数は18機にとどまり、実戦での目立った活躍もないが、本機の製造から運用に至る経験は、後のゴータ社Gシリーズ重爆撃機の成功の礎となった。
アイコンは、第2期生産機。それまで明確な役割のなかった中席に防御機銃が備えられ、主脚間には爆弾の搭載・投下を容易にするコンテナが追加装備されている。
運動性の低さや転覆時の危険性、胴体尾部の強度不足等の問題から生産数は18機にとどまり、実戦での目立った活躍もないが、本機の製造から運用に至る経験は、後のゴータ社Gシリーズ重爆撃機の成功の礎となった。
アイコンは、第2期生産機。それまで明確な役割のなかった中席に防御機銃が備えられ、主脚間には爆弾の搭載・投下を容易にするコンテナが追加装備されている。

(2002/10/16更新)
後に一時代を築くユンカース金属機の最初の実用機。同時に、Il-2シュトルモヴィクに先駆けること約20年にして「バスタブ型装甲区画構造」を採用し、非常に冗長性の高いトラス構造の翼骨組とあいまって、無類の撃たれ強さを誇った地上攻撃機でもある。
金属機といっても、後の同社機のような全面波板張りではなく、尾部胴体(生産時期によっては尾翼も)は金属骨組みに羽布張りとなっているため、装甲区画ともども胴体表面は平滑になっている。
その先進性ゆえに戦後もしばらく開発が継続され、尾部胴体を波板張りとした機体も少数完成している。
金属機といっても、後の同社機のような全面波板張りではなく、尾部胴体(生産時期によっては尾翼も)は金属骨組みに羽布張りとなっているため、装甲区画ともども胴体表面は平滑になっている。
その先進性ゆえに戦後もしばらく開発が継続され、尾部胴体を波板張りとした機体も少数完成している。

(2007/1/9更新)
新興企業LVGが、仏ニューポール社製高速単葉機の設計で名を馳せたフランツ=シュナイダーを招聘して開発した機体。1914年のハインリヒ皇弟杯飛行大会の上位を独占した操縦性・上昇力・滞空性能に加え、良好な視界、連絡容易な前後席配置、カメラや小型爆弾を収容可能な機内空間、分解輸送しやすい構成等、実用性の高い設計が評価され、WW1開戦時にはドイツ陸軍航空隊の非武装複座複葉機の約半数を占めるまでの大量採用にいたった。初期生産機に強度不足があったとはいえ、ベンツ、アルグス、メルセデス各社製エンジンが搭載でき、多様な運用環境に適応でき、取扱いも容易な本機は、前線での活動こそ1915年後半までには後継機に道を譲ったが、安全で維持の容易な練習機として終戦まで使い続けられ、1920年代まで飛行していた機体もある。生産数はババリアのオットー社でのライセンス生産分を含めて600機前後とみられる。
アイコンは、初期生産機。主脚前方に突き出した転覆防止用ソリは後に廃止されている。
アイコンは、初期生産機。主脚前方に突き出した転覆防止用ソリは後に廃止されている。

(2002/10/4更新)
(2005/4/11更新)
それまで下請生産していたローラント社機に範をとり、木製モノコックの滑らかな胴体、斜めにカットされた主翼・水平尾翼翼端、「つ」の字型に整えられた垂直尾翼、下翼フィレットと、すべてが端整に、いかにもドイツ的な美しさで作られた機体。しかし、同エンジン(メルセデス160馬力)の他機種に比べて速度が低めで運動性にも劣るため、対戦闘機戦は不得手であり、高い構造強度が生かせる対気球攻撃(上空哨戒から急降下でいったん下に出てから急上昇に転じて減速し、気球との速度差を減らす)を得意とした。
重量や翼面積の点で特段のハンデのない本機の性能が低迷した要因は、ピッチが浅いプロペラとエンジンのミスマッチ、前後のずれが少なく互いに空力干渉しやすい上下主翼、面積が大きめで高速時に重くなる補助翼等の要因が重なった総合的なものだと思われる。
初期型D.IIIが約260機、操作・照準がしやすいように胴体内埋め込み式の機銃を機首上面に移す等した小改良型D.IIIaが約750機作られた。
重量や翼面積の点で特段のハンデのない本機の性能が低迷した要因は、ピッチが浅いプロペラとエンジンのミスマッチ、前後のずれが少なく互いに空力干渉しやすい上下主翼、面積が大きめで高速時に重くなる補助翼等の要因が重なった総合的なものだと思われる。
初期型D.IIIが約260機、操作・照準がしやすいように胴体内埋め込み式の機銃を機首上面に移す等した小改良型D.IIIaが約750機作られた。
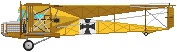
(2002/11/29更新)
来るべき大量航空輸送時代を夢見ていたシュテッフェン兄弟が、戦時に乗じて国の金で超大型機の研究をしようとダメモトで当局に企画を出したら開発が決定してしまった機体。陸軍の差配により鉄道車両で有名なジーメンス社から製造施設と技術支援の提供を得て建造された。
機首に2基、コクピット下に1基のベンツBz.IIIエンジン(150馬力)を搭載、出力をギアボックスでひとつにまとめて胴体側面のシャフトから両翼のプロペラに分岐するシステムを採用して、飛行中のエンジン修理・調整を可能にし、またプロペラ後方をクリアにして推進効率を高めようとした。
テスト飛行(スタッフ移動にかこつけて旅客輸送実験もしたらしい)では、ペイロード1200kgにて128km/h、到達高度3700mを記録する等そこそこの性能を示し、機体中心に集中した重量物と全操縦翼面に備えられたサーボタブのおかげで操縦性も良かった。しかし、アンダーパワー、前下方視界の悪さ、爆弾投下後の重心移動等が問題となり、パワーアップ(2〜7号機では260馬力×3)や内部配置の見直し等が行われたが、エンジンの信頼性改善や度重なる不時着の修理に追われ、結局、5号機が作戦飛行を2回成功させただけで、ジーメンス社に鉄道車両用の軽量大容量ギアボックスの技術を残したとはいえ、航空技術史的にはただのイロモノで終わってしまった。
アイコンは、初期飛行テストにおける状態。上下二股になった尾部は、主翼後縁間の防御銃座からの射界を確保するためのものである。
機首に2基、コクピット下に1基のベンツBz.IIIエンジン(150馬力)を搭載、出力をギアボックスでひとつにまとめて胴体側面のシャフトから両翼のプロペラに分岐するシステムを採用して、飛行中のエンジン修理・調整を可能にし、またプロペラ後方をクリアにして推進効率を高めようとした。
テスト飛行(スタッフ移動にかこつけて旅客輸送実験もしたらしい)では、ペイロード1200kgにて128km/h、到達高度3700mを記録する等そこそこの性能を示し、機体中心に集中した重量物と全操縦翼面に備えられたサーボタブのおかげで操縦性も良かった。しかし、アンダーパワー、前下方視界の悪さ、爆弾投下後の重心移動等が問題となり、パワーアップ(2〜7号機では260馬力×3)や内部配置の見直し等が行われたが、エンジンの信頼性改善や度重なる不時着の修理に追われ、結局、5号機が作戦飛行を2回成功させただけで、ジーメンス社に鉄道車両用の軽量大容量ギアボックスの技術を残したとはいえ、航空技術史的にはただのイロモノで終わってしまった。
アイコンは、初期飛行テストにおける状態。上下二股になった尾部は、主翼後縁間の防御銃座からの射界を確保するためのものである。

(2002/9/23更新)
(2003/8/16更新)
(2005/8/1更新)
(2007/4/10更新)
究極の回転式空冷エンジンSh.III(160hp)を搭載する高速戦闘機として開発され、従来のドイツ戦闘機の倍ともいわれる上昇率を誇ったが、エンジンの完成の遅れや過大なプロペラ直径による着陸操作の難しさ(審査中に小直径4翅に換装)、より高性能を求める陸軍航空隊の要求に応えるための改良などに手間取り、本格的に量産が始まったのは敗戦直前、しかも配備先は本土防空部隊中心だったため、目立った活躍をすることなく終わってしまった。
アイコンは、かのエルンスト=ウーデットの愛機。LO!とは、婚約者ロロ=ツィンクの愛称。
アイコンは、かのエルンスト=ウーデットの愛機。LO!とは、婚約者ロロ=ツィンクの愛称。
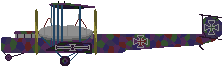
(2003/9/23更新)
1915年のV.G.O.I以来試作と試験運用にとどまっていたツェッペリン社製重爆撃機で初めて量産(18機)にこぎつけた機体。
メカニズム的にはタンデム式エンジンナセル2組にマイバッハ245馬力又はメルセデス260馬力4基を装備する堅実な設計だが、爆弾等裁量最大2トン、最大航続時間10時間と他を寄せ付けない性能を誇り、英本土夜間爆撃等に活躍した。
メカニズム的にはタンデム式エンジンナセル2組にマイバッハ245馬力又はメルセデス260馬力4基を装備する堅実な設計だが、爆弾等裁量最大2トン、最大航続時間10時間と他を寄せ付けない性能を誇り、英本土夜間爆撃等に活躍した。

(2005/4/11更新)
WW1前半においてカプロニ重爆以外の自国設計機を持たなかったイタリア航空界の状況を打破するため、サヴォヤ、ヴェルドゥティオ両技師が中心となって設計した機体。折しも軽量高出力のSPA水冷6気筒エンジンが完成したことから、造船・兵器産業大手のアンサルド社が名乗りを上げて生産にこぎつけた。機種名のSVAは設計・製造にあたった三者の頭文字。
良質の木材や鋼管が入手困難だったこともあり、尾部を逆三角形断面としてフレームに頼らずに歪みを防ぐ合板外皮の胴体やW型の翼間支柱等、構造設計には独自のものがみられる。大きめのエンジンと大型燃料タンクのために操縦席前方の胴体が長く高くなって機首銃の操作性と前方視界に難があり、また、運動性が良くないことから、戦闘機としての使用は早々に断念されたが、巡航160km/h超、最高230km/hの高速と最大7時間近い航続性能を活かした高速偵察・爆撃機として大いに活躍し、安定性を買われて練習機としても長く使われた。殊に長距離偵察・攻撃は本機の独壇場であり、1918年8月9日には、往復1005kmを翔破してのウィーンへの降伏勧告ビラ散布(文面作者の詩人ダヌンツィオも同行)を成功させている。
アイコンは、1918年初めの生産と思われる単座型。単座・複座、爆撃装備の有無、水上機等の各型を合わせた戦中の生産機数は約1300機。戦後も1923年までに700機程度が生産されており、民間で活躍した機体も多い。
良質の木材や鋼管が入手困難だったこともあり、尾部を逆三角形断面としてフレームに頼らずに歪みを防ぐ合板外皮の胴体やW型の翼間支柱等、構造設計には独自のものがみられる。大きめのエンジンと大型燃料タンクのために操縦席前方の胴体が長く高くなって機首銃の操作性と前方視界に難があり、また、運動性が良くないことから、戦闘機としての使用は早々に断念されたが、巡航160km/h超、最高230km/hの高速と最大7時間近い航続性能を活かした高速偵察・爆撃機として大いに活躍し、安定性を買われて練習機としても長く使われた。殊に長距離偵察・攻撃は本機の独壇場であり、1918年8月9日には、往復1005kmを翔破してのウィーンへの降伏勧告ビラ散布(文面作者の詩人ダヌンツィオも同行)を成功させている。
アイコンは、1918年初めの生産と思われる単座型。単座・複座、爆撃装備の有無、水上機等の各型を合わせた戦中の生産機数は約1300機。戦後も1923年までに700機程度が生産されており、民間で活躍した機体も多い。

(2005/4/13更新)
1919年、イタリア政府は第一次大戦の戦勝国としての威容と軍事航空の実力を世に示すため、同じく戦勝国である日本までの大飛行計画を発動した。動員されたのはカプロニ重爆撃機4機とSVA9練習機7機だが、ほとんどの機体は荒天やアラブ・インドの反乱勢力の襲撃によってリタイアしてしまっている。結局、日本に到達したのは第二陣として1920年2月14日にローマを出発したフェラーリン大尉・カンパーニ曹長ペアとマジェーロ中尉・マレット伍長ペアのみ、しかも後者は中国で予備機に乗り換えているため、アイコンのフェラーリン機だけが 107日間・総行程18000kmを飛びきったことになる。
フェラーリン・マジェーロ両名の愛機は日本に寄贈され、靖国神社遊就館に展示されていたが、空襲で焼失している。現在、航空自衛隊浜松広報館エアーパークに展示されているのは、1970年の大阪万博イタリア館の展示物として作られたレプリカである。
フェラーリン・マジェーロ両名の愛機は日本に寄贈され、靖国神社遊就館に展示されていたが、空襲で焼失している。現在、航空自衛隊浜松広報館エアーパークに展示されているのは、1970年の大阪万博イタリア館の展示物として作られたレプリカである。
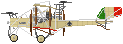
(2003/7/27更新)
ジュリオ=ドゥーエの戦略空軍構想に共鳴し、その援助を得たカプロニの設計になる世界初の重爆撃機。当初からアルプス山脈・アドリア海越えの作戦を想定していたため、余剰馬力と冗長性に優れる三発形式とされた。エンジンは双ブームの翼面上部分と中央胴体の後端に置かれているため、飛行中のアクセスも容易である。
頑丈な構造、最大9時間超の航続性能、良好な高空性能と操縦安定性、そして搭載能力に恵まれた本機は、本来の爆撃に加えて、偵察、雷撃、輸送、大型機操縦訓練、1インチ自動砲を装備しての夜間防空までさまざまな任務をこなし、1927年まで現役だった機体もある。大戦中の生産機数は461機。このほかにフランスでのライセンス生産分(89機?)がある。
アイコンは初期生産型に夜間飛行用のライトと中央胴体前後端の防御銃座を追加装備した機体で、パグリアーノ・ゴリ両名の操縦により、詩人ダヌンツィオが偵察員兼銃手として出撃したことで有名。
頑丈な構造、最大9時間超の航続性能、良好な高空性能と操縦安定性、そして搭載能力に恵まれた本機は、本来の爆撃に加えて、偵察、雷撃、輸送、大型機操縦訓練、1インチ自動砲を装備しての夜間防空までさまざまな任務をこなし、1927年まで現役だった機体もある。大戦中の生産機数は461機。このほかにフランスでのライセンス生産分(89機?)がある。
アイコンは初期生産型に夜間飛行用のライトと中央胴体前後端の防御銃座を追加装備した機体で、パグリアーノ・ゴリ両名の操縦により、詩人ダヌンツィオが偵察員兼銃手として出撃したことで有名。
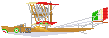
(2006/12/15更新)
1915年5月27日深夜のヴェネツィア爆撃作戦中にエンジントラブルで不時着水したオーストリア=ハンガリー海軍のローナーT飛行艇を鹵獲・調査したイタリア海軍は、その高性能にほれ込み、自軍の航空戦力立上げに不可欠の機材として、マッキ社(仏ニューポールと提携中)にコピー生産を命じた。マッキでは未経験の木製艇体の製造を急遽地元の船工場に発注、エンジンは自国製イソッタ=フラスキニ150馬力を装備して、早くも同年9月には1号機を完成、10月末には部隊配備も開始された。1916年中盤までに約140機が新規製造または鹵獲したローナー機から修復され、コピー元の敵機と同様、偵察、爆撃、洋上哨戒、防空等に活躍、後継機に道を譲ってからも、生来の操縦の容易さと堅牢さから、練習機に改装されて長く使われた。
アイコンは、最終期生産型L232号機。風防がイタリア独自設計のものとなっているほか、ローナーTlの鹵獲・調査後に製造されたため、翼間支柱は同型仕様の片側2組となっている。本来、この新型主翼は軽量化戦闘機型L.2のために用意されたものだが、ローナーT仕様の片側3組の支柱の主翼を持っていた従来型のL.1にも、修理などを機にこちらに換装されたものがみられる。
アイコンは、最終期生産型L232号機。風防がイタリア独自設計のものとなっているほか、ローナーTlの鹵獲・調査後に製造されたため、翼間支柱は同型仕様の片側2組となっている。本来、この新型主翼は軽量化戦闘機型L.2のために用意されたものだが、ローナーT仕様の片側3組の支柱の主翼を持っていた従来型のL.1にも、修理などを機にこちらに換装されたものがみられる。

(2007/1/9更新)
アドリア海上の航空戦の激化に伴って護衛・迎撃戦闘機が必要となり、また、ハンザ=ブランデンブルクC.C戦闘飛行艇の投入で先行していた墺洪帝国海軍に対抗するために開発された機体。マッキでは、艇体やエンジン架をコピー機の生産で手馴れた墺ローナーL系列飛行艇に、主翼を提携関係にあった仏ニューポール製戦闘機に範をとった構成としたが、尾翼操縦系統や機銃の艤装等には独自の設計がみられる。機銃の故障を頻発する悪癖はあったものの、飛行艇としては限界ともいえる小型の機体に190馬力のエンジンを組み合わせた結果、同盟軍陸上戦闘機にさえ匹敵しうる飛行性能を実現し、パイロットにも絶賛された。外海での運用はほぼ不可能だったとはいえ、アドリア海上の制空権確保には期待通りの活躍を見せ、生産数も348機に達している。しかし、後継機M.7が早期に完成したことから、戦後は急速に退役していった。
アイコンは、第255飛行隊所属の初期型。日本では機番「4」は紅の豚ことマルコ=パゴットの乗機として有名だが、こちらはれっきとした実在機である。支柱と一体化したフェアリングを持ち翼下面に密着した翼端フロートは、中期型以降では通常の形式に改められている。
アイコンは、第255飛行隊所属の初期型。日本では機番「4」は紅の豚ことマルコ=パゴットの乗機として有名だが、こちらはれっきとした実在機である。支柱と一体化したフェアリングを持ち翼下面に密着した翼端フロートは、中期型以降では通常の形式に改められている。

(2006/7/10更新)
製粉機・レンガ製造設備メーカーであったSAMLは、墺アヴィアティク製P.13のライセンス生産から航空機産業に参入、1915年5月にイタリアがWW1に参戦すると、アヴィアティクを退職していたロベルト=ヴィルトに新型多用途機の設計を依頼した。初飛行までの開発は順調に進行し、当局も大量発注を予定したが、エンジンの開発・生産が追いつかず、本機の配備が本格化したのは1916年末になってからだった。
性能的には平凡な機体であったが、巧みなコクピット配置と後退翼がもたらす良好な下方視界、独特のバランス機構を有する後席銃架、余裕のある機内スペース、信頼性の高さといった点で実用性は高く、偵察や砲兵観測はもとより、操縦練習、地上攻撃、防空戦闘、果ては物資輸送にまで活用され、戦後もしばらくアフリカ植民地派遣軍などで使用された。生産数は、三張間の主翼を持つ初期型S.1と合わせて657機。
アイコンは、1918年中頃、第118飛行中隊に配備されていた機体。
性能的には平凡な機体であったが、巧みなコクピット配置と後退翼がもたらす良好な下方視界、独特のバランス機構を有する後席銃架、余裕のある機内スペース、信頼性の高さといった点で実用性は高く、偵察や砲兵観測はもとより、操縦練習、地上攻撃、防空戦闘、果ては物資輸送にまで活用され、戦後もしばらくアフリカ植民地派遣軍などで使用された。生産数は、三張間の主翼を持つ初期型S.1と合わせて657機。
アイコンは、1918年中頃、第118飛行中隊に配備されていた機体。

(2003/7/27更新)
フランス軍向けの生産が優先されたため入手しにくく、性能的にも不満足な点があったニューポール17に代わる戦闘機として、在仏イタリア軍用航空使節団がフランスの中堅企業アンリオ社に提示した仕様に基づいて作られた機体。それまでライセンス生産してきた英ソッピース社の機体に範をとりつつ、下翼を後方に下げて前下方視界を広くし、尾翼容積に余裕を持たせて安定性を確保する等、使いやすさを意識した設計となっている。
同じエンジンを積んだニューポール17より若干重くはなったが、速度と上昇率で若干勝り、航続時間は40〜80%長く、低翼面荷重と最大荷重9Gにも達する機体強度のおかげでより激しい空戦機動が可能だった。生産機のほとんどはイタリア軍で使われ、フランスでは海軍が少数購入したのみだが、ベルギーやスイスにも輸出されたほか、戦後も1920年代末まで現役にあり、記録飛行やレースにも活躍した。
アイコンは、のちに訪日大飛行で有名になるアルトゥーロ=フェラーリンが第82飛行隊に所属していたときの乗機。
同じエンジンを積んだニューポール17より若干重くはなったが、速度と上昇率で若干勝り、航続時間は40〜80%長く、低翼面荷重と最大荷重9Gにも達する機体強度のおかげでより激しい空戦機動が可能だった。生産機のほとんどはイタリア軍で使われ、フランスでは海軍が少数購入したのみだが、ベルギーやスイスにも輸出されたほか、戦後も1920年代末まで現役にあり、記録飛行やレースにも活躍した。
アイコンは、のちに訪日大飛行で有名になるアルトゥーロ=フェラーリンが第82飛行隊に所属していたときの乗機。

(2007/1/9更新)
フランス機の導入で強化されたイタリア・ロシア両軍航空戦力に対抗するため、輸入機フォッカーE.IIIの後継機たるべく開発された機体。ハインケル設計の原型機「KD」が実用性皆無だったため、量産までには胴体形状、ラジエター配置、翼間支柱等の改設計を要した。翼面を底としてピラミッド状に組んだ支柱を上下翼間の一点で結合して翼組形状を保つ「星形支柱」が特徴だが、張線を廃して製造・整備が楽になった反面、空力・重量の面では少し損をしていたようである。また、背の高いエンジンによる前方視界不良、垂直尾翼面積過小による悪性のスピン癖、上昇・高空性能の絶望的不足等、戦闘力は到底満足できる水準ではなく、箱型の木製モノコック胴体をもじって「空飛ぶ棺桶」の悪名を奉られた。フェニックス社製造分ではエンジン強化、座席位置上昇、支柱端部空力整形、垂直尾翼拡大(後期型)等により若干の改善をみたが、それでも協商軍戦闘機に対して不利な戦いを強いられ続けている。生産数は122機(うちフェニックス製72機)。
アイコンは、墺洪帝国第4位のエース、フランク=リンケ・クロウフォード(撃墜数27)が初戦果を挙げた際の乗機(フェニックス製中期型)。上翼には、標準武装としてシュワルツローゼ機銃と弾薬を収めたVK2ガンポッドを装備している。
アイコンは、墺洪帝国第4位のエース、フランク=リンケ・クロウフォード(撃墜数27)が初戦果を挙げた際の乗機(フェニックス製中期型)。上翼には、標準武装としてシュワルツローゼ機銃と弾薬を収めたVK2ガンポッドを装備している。
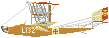
(2006/12/15更新)
1913年の「一葉半型」以来、オーストリア=ハンガリー海軍に飛行艇を納入し続けてきたローナー社が、ラップ、ヒエロ等の新型140〜160馬力級エンジンを搭載する実戦的な多用途複座飛行艇として開発した機体。1914年末に完成した基本型ローナーT(1915年春から実戦投入)は翼間支柱が片側3組だったが、本型では片側2組とされ、併せて機体構造の軽量化、上下翼の面積比の見直し等も行われ、量産化後も防弾装備の追加や燃料系統の改良等が重ねられたため、堅牢性、水上安定性、航続時間(6時間以上)に加えて操縦性や実用性も高水準でまとめられた傑作機となった。コクピットは偵察/兵装操作員席がやや後方にずらされた並列複座で、防波性、視界、兵装操作系等が順次改善されたため、風防周辺の造形にはバリエーションが多い。
WW1前半においては、偵察、爆撃、洋上哨戒、防空等に活用され、海況が許せば外海での運用も可能なことから、アドリア海全域で活躍したが、1917年末までには後継機に道を譲って第一線を退いている。1916年9月までにタイプTと合せて107機が製造(イタリア製コピー機マッキL.1鹵獲機の修復を含む?)されたが、その約2/3は、政府のハンガリー地域振興政策に沿って設立されていたハンガリー航空機株式会社(UFAG)製である。
アイコンは、1916年9月15日、僚機L135号機とともに世界初の航空機による潜水艦(仏海軍フォコー)撃沈に成功したコニォビッツ大尉・セヴェーラ見習士官乗機L132号機。
WW1前半においては、偵察、爆撃、洋上哨戒、防空等に活用され、海況が許せば外海での運用も可能なことから、アドリア海全域で活躍したが、1917年末までには後継機に道を譲って第一線を退いている。1916年9月までにタイプTと合せて107機が製造(イタリア製コピー機マッキL.1鹵獲機の修復を含む?)されたが、その約2/3は、政府のハンガリー地域振興政策に沿って設立されていたハンガリー航空機株式会社(UFAG)製である。
アイコンは、1916年9月15日、僚機L135号機とともに世界初の航空機による潜水艦(仏海軍フォコー)撃沈に成功したコニォビッツ大尉・セヴェーラ見習士官乗機L132号機。

(2006/6/15更新)
1917年初めにハンガリー航空機工業株式会社(UFAG)が完全国内資本化されて成立したフェニックス社が同年の新戦闘機コンペに応募して採用された機体。胴体はハンザ=ブランデンブルクD.Iのものを若干延長しただけだが、エドムント=シュパルマンの設計になる新型主翼とヒエロ200馬力エンジンの装備によって面目を一新している。重量がやや過大で、コクピットから機銃へのアクセス性が悪い等の欠点があり、速度と上昇性能では英仏伊の新型戦闘機群にやや劣っていたが、操縦性・安定性に優れ、機体強度も高かったので、一応はWW1後半の主力戦闘機としての水準に到達していたといえる。改良型D.IIの登場までに約140機が作られて陸海軍の多くの部隊に配備され、終戦時にも60〜70機程度が残存していたという。
アイコンは、オーストリア=ハンガリー海軍のステファン=ウルマン少尉の乗機。
アイコンは、オーストリア=ハンガリー海軍のステファン=ウルマン少尉の乗機。

(2006/6/15更新)
前作D.Iを軽量化し、動翼を再設計して機動性を高めた改良型。軽量化に伴う構造強度の低下が不安視されたほか、初期生産分で発動機架や主翼の工作不良による事故があったために戦列化は1918年5月後半までずれ込み、エンジンや機銃の供給不足もあったため、終戦までの生産数は、230馬力エンジンに換装された後期型D.IIaとあわせても96機にとどまり、華々しい戦果にも恵まれなかった。しかし、パイロットには総じて好評であり、改良型D.IIIがライセンス生産のフォッカーD.VIIと並ぶ重点整備機種とされていたことからも、本機の評価の高さがうかがわれる。
アイコンは、オーストリア=ハンガリー陸軍第55戦闘機隊の小隊長、アレクサンダー=カスツァ(最終撃墜数7)乗機D.IIa。尾部のハートマークは、同僚ヨセフ=キッスの死を悼んでのものだという。
アイコンは、オーストリア=ハンガリー陸軍第55戦闘機隊の小隊長、アレクサンダー=カスツァ(最終撃墜数7)乗機D.IIa。尾部のハートマークは、同僚ヨセフ=キッスの死を悼んでのものだという。

(2006/6/15更新)
1916年後半、国産戦闘機の性能不足に直面したオーストリア=ハンガリーは、当時最新のドイツ戦闘機アルバトロスD.IIIのライセンス生産権を取得、1917年1月からオーストリア航空機製造株式会社(Öffag)で量産を開始した。国産化にあたっては、エンジンをオーストロ=ダイムラー製に換え、シュワルツローゼ機銃を機首埋込み式に装備し、捻り荷重に弱かった下翼の構造を強化する等の仕様変更が行われている。ドイツ製の機体よりも速度・上昇力・急降下性能でやや上回ったが、重心が前進して操縦性が悪化していたともいわれる。エンジン出力によって53(185馬力・一部はD.II仕様)、153(200馬力)、253(225馬力)の各シリーズがあり、総生産数は530〜550機に達した。戦後のオーストリア=ハンガリーの崩壊に伴って東欧諸国空軍に流出した機体の中には、1920年代中盤まで現役だったものもある。
アイコンは、ハンガリー地域出身では第一位のエース、ヨセフ=キッス(最終撃墜数19)乗機シリーズ253。機首上面のシリンダ部カバーは省略されている機体が多い。
アイコンは、ハンガリー地域出身では第一位のエース、ヨセフ=キッス(最終撃墜数19)乗機シリーズ253。機首上面のシリンダ部カバーは省略されている機体が多い。

(2006/6/15更新)
WW1開戦直後、まともな航空兵力を有しなかったオーストリア=ハンガリーは、ドイツからの輸入によって国内生産の不足を補うことにした。この中には、大戦序盤の最強戦闘機であるフォッカーE.IIIも含まれており、A.IIIの名称で使用されている。しかし、ヒマシ油をほとんど産出しないオーストリア=ハンガリーでは、潤滑油消費量の多い回転式空冷エンジンを装備する本機が大規模に使われることはなく、導入数は14機のみで、ライセンス生産が行われることもなかった。

(2002/9/25更新)
世界で初めて有人動力飛行(1903年12月17日、ノースカロライナ州キティホーク)に成功した機体。この飛行のために積み重ねてきたグライダーによる飛行実験や翼型試験装置による研究成果の集大成だけあって、同時期の機体の中では抜きん出た操縦性と推進効率とを誇った。ただし、レバーと腰の振りによる操縦方式はかなり微妙な操作を要求し、ライト兄弟以外に本機をまともに操縦できる者はいなかったともいう。

(2002/9/22更新)
(2003/8/16更新)
寒冷地用に降着装置をスキー式に改造してある。
機銃もフランス軍仕様のオチキスからルイスに換装されている。
機銃もフランス軍仕様のオチキスからルイスに換装されている。
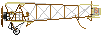
(2004/3/21更新)
元海軍技士・臨時軍用気球研究会研究員にして旧島津藩士の男爵家の嗣子である奈良原三次が、私財を投じて製作した機体。1910年夏の1号機がエンジン(アンザニ25馬力)の馬力不足と操縦系の洗練不足のために滑走練習程度にしか使えなかったことを教訓に、エンジンをノーム50馬力(1号機が当初予定していたエンジンでもある)に強化、上下翼の食いちがいを少なくし、主翼前縁に昇降舵(補助翼とも)を置くスタイルを通常の形式に改める等の改良を施した。また、脚をわざと壊れやすく設計し、ハードランディング時の衝撃を脚の破壊で吸収することで機体と乗員を守るように配慮されていた。
1911年5月5日、奈良原自らの操縦により高度4m・距離60mの水平飛行に成功し、国産機としての初飛行に成功した。しかし、重量・翼面積が過大で性能的に満足なものではなかったため、その後はもっぱら練習用の機材とされた。
1911年5月5日、奈良原自らの操縦により高度4m・距離60mの水平飛行に成功し、国産機としての初飛行に成功した。しかし、重量・翼面積が過大で性能的に満足なものではなかったため、その後はもっぱら練習用の機材とされた。

(2003/1/14更新)
(2003/6/8更新)
1911年5月に奈良原式2号機で国産機初飛行を成し遂げた奈良原三次が、暴風事故と資金調達の不手際から失われた3号機に続いてほぼ同仕様で作り上げた機体。3号機と比べて材料・構造にコスト削減の工夫がこらされており、全国各地を巡回して有料飛行大会を開催することで日本で初めて採算ベースでの運行が図られた航空機でもある。エンジンにブレリオXI量産型と同じノーム50馬力を採用したこともあって、当時としては安定した性能と信頼性を持ち、見世物とはいえ、日本各地に飛行機時代の到来を告げる役目を果たした。
黎明期の常としてほとんど飛行ごとに改修を重ねた機体である(少なくとも胴体延長2回、補助翼操作系統改修1回、降着装置改修1回、垂直尾翼交換3回が確認できる)が、アイコンは、比較的性能が安定し、現在の千葉市美浜区を拠点に活動していた明治45年後半の状態(広島練兵場での興行時の写真を参考)とした。
黎明期の常としてほとんど飛行ごとに改修を重ねた機体である(少なくとも胴体延長2回、補助翼操作系統改修1回、降着装置改修1回、垂直尾翼交換3回が確認できる)が、アイコンは、比較的性能が安定し、現在の千葉市美浜区を拠点に活動していた明治45年後半の状態(広島練兵場での興行時の写真を参考)とした。
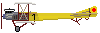
(2003/12/16更新)
(2003/12/17更新)
大正5年、陸軍の制式規格に基づいて制作された。日本人の独創による国産機の第一歩がこの機あたりから始まった。
最大速度:110km/h 武装:後上旋回機銃×1
発動機:ダイムラー水冷式直列型6気筒 100馬力
航続時間:4〜6h
最大速度:110km/h 武装:後上旋回機銃×1
発動機:ダイムラー水冷式直列型6気筒 100馬力
航続時間:4〜6h
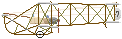
(2003/12/22更新)
前年に輸入した1912年型1機に続いて、1913(大正2)年に陸軍がフランスから4機を輸入した機体。陸軍機として初めて部隊編成を行い、1914年の青島攻略作戦に参加して偵察、爆撃等を行った。また、陸軍砲兵工廠で22機、臨時軍用気球研究会で4機がライセンス生産されている。
なお、本機の設計者モーリス=ファルマンの兄アンリは、日本初飛行で有名なアンリ・ファルマン機の設計者である。
全長:12.00m 全幅:15.50m
全高:3.66m 主翼面積:60.00m2
乗員:2人
発動機:ルノー空冷式V型8気筒 70馬力
最大速度:90km/h 航続時間:4h
なお、本機の設計者モーリス=ファルマンの兄アンリは、日本初飛行で有名なアンリ・ファルマン機の設計者である。
全長:12.00m 全幅:15.50m
全高:3.66m 主翼面積:60.00m2
乗員:2人
発動機:ルノー空冷式V型8気筒 70馬力
最大速度:90km/h 航続時間:4h

(2004/01/06更新)
1913(大正2)年にモーリス・ファルマン機の前方昇降舵を取り除いた「改造モ式」が作られたが、この機体の操縦ナセルを上下翼の中間に位置させ、2枚の垂直尾翼を小さくし、降着用橇を短くした機体が所沢で少数製作された。大正5年8月より陸軍航空隊隊で使用され、大正7年8月にはシベリア出兵に出動した。
全長:9.33m 全幅:15.50m
主翼面積:58.0m2 乗員:2名
発動機:ルノー空冷式V型8気筒 70馬力
最大速度:90km/h 実用上昇限度:3000m
航続時間:4h 武装:必要に応じ機首に機銃×1
全長:9.33m 全幅:15.50m
主翼面積:58.0m2 乗員:2名
発動機:ルノー空冷式V型8気筒 70馬力
最大速度:90km/h 実用上昇限度:3000m
航続時間:4h 武装:必要に応じ機首に機銃×1

(2004/01/06更新)
1917(大正6)年5月に完成した国産機。大正7年4月以降多数製作され、同年のシベリア出兵にも出動した。結局、改造モ式は4・5・6型にわたって大正10年までに軍民合わせて150機以上が作られた。現存する最古の国産機でもある。
全長:9.33m 全幅:16.13m
主翼面積:62.0m2 乗員2名
発動機:ダイムラー水冷式直列6気筒 100馬力
最大速度:110km/h 巡航速度:90km/h
実用上昇限度:3500m 航続時間:5h
全長:9.33m 全幅:16.13m
主翼面積:62.0m2 乗員2名
発動機:ダイムラー水冷式直列6気筒 100馬力
最大速度:110km/h 巡航速度:90km/h
実用上昇限度:3500m 航続時間:5h

(2003/12/17更新)
(2003/12/21更新)
1917〜18(大正6〜7)年に陸軍がフランスから購入したニューポール24型を制式兵器としたもの。80馬力の練習機型と120馬力の戦闘機型があり、大正8年3月以降、補給部所沢支部で国産化された。戦闘機型は大正11年5月以降、実用性で劣る丙式1型(スパッド13)戦闘機に代わり戦闘隊に支給され、大正15年12月まで使用された。両型合わせて300機以上と、当時としては画期的な数が生産された。
全長:5.67m 全幅:8.22m
(練習機型)
発動機:ル・ローヌC型空冷式回転星形9気筒80馬力
最大速度:137km/h 航続時間:2h
実用上昇限度:5000m
(戦闘機型)
発動機:ル・ローヌJ型空冷式回転星形9気筒120馬力
最大速度:163km/h 航続時間:2h
実用上昇限度:6000m 武装:7.7mm機銃×1
全長:5.67m 全幅:8.22m
(練習機型)
発動機:ル・ローヌC型空冷式回転星形9気筒80馬力
最大速度:137km/h 航続時間:2h
実用上昇限度:5000m
(戦闘機型)
発動機:ル・ローヌJ型空冷式回転星形9気筒120馬力
最大速度:163km/h 航続時間:2h
実用上昇限度:6000m 武装:7.7mm機銃×1

(2004/4/9更新)
甲式三型(ニューポール24)・丙式一型(スパッド13)両戦闘機の後継機として日本陸軍が1922年から導入したニューポール29の日本仕様。輸入機78機に加えて、1923年からは中島飛行機で、1925年からは砲兵工廠でライセンス生産を開始、それぞれ608機、46機が作られた。
整備性やエンジンの信頼性に問題があり、国産機では木製モノコック胴体が規格内の重量で製造できなかったために性能が若干低下したが、それでも操縦性と上昇力に優れた機体であり、パイロットには好まれた。1933年には第一線を引いたが、訓練部隊では1937年まで現役にあったという。
整備性やエンジンの信頼性に問題があり、国産機では木製モノコック胴体が規格内の重量で製造できなかったために性能が若干低下したが、それでも操縦性と上昇力に優れた機体であり、パイロットには好まれた。1933年には第一線を引いたが、訓練部隊では1937年まで現役にあったという。

(2006/5/30更新)
1917年に訪欧した日本陸軍視察団は、サルムソン2A2の性能と多任務適合性に注目、 1919年のフランス航空使節団持込みの機体を皮切りに80機の輸入を開始した。一方、1920年から所沢の航空補給部支部において修理の名目で海賊版の製造に着手、日仏間の外交問題になりかけたが、それ以前に自社負担でライセンス生産権を購入していた川崎造船所のあっせんによって正規のライセンス生産に移行している。
1927年までに官民合わせて607機を国産し、軍用機としては1933年まで偵察、爆撃、連絡、練習などに使用されたほか、民間への払下げ機が新聞社や飛行学校で多用されたこともあって、戦前日本において最もよく見かける機体のひとつであった。
アイコンは、飛行第二連隊所属機とみられる機体。
1927年までに官民合わせて607機を国産し、軍用機としては1933年まで偵察、爆撃、連絡、練習などに使用されたほか、民間への払下げ機が新聞社や飛行学校で多用されたこともあって、戦前日本において最もよく見かける機体のひとつであった。
アイコンは、飛行第二連隊所属機とみられる機体。
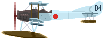
(2004/1/14更新)
1917(大正6)年、前年に輸入したショート184水上機を参考に、馬越大尉と中島知久平との協力で設計・製作された国産水上偵察機。それまでの海軍機には見られない優秀な実用性を示した。翌年制式化されて横須賀海軍工廠で32機を生産、大正8年以降は発動機を三菱ヒ式200馬力に換装した後期生産型が愛知と中島で186機作られた。
全長:10.20m 全幅:15.69m
全高:3.67m 主翼面積:48.22m2
乗員:2名
発動機:三菱ヒ式水冷式V型8気筒200〜220馬力
最大速度:155.6km/h 航続時間:10h
全長:10.20m 全幅:15.69m
全高:3.67m 主翼面積:48.22m2
乗員:2名
発動機:三菱ヒ式水冷式V型8気筒200〜220馬力
最大速度:155.6km/h 航続時間:10h

(2003/4/13更新)
1921年、航空機の早期戦力化の必要に迫られた日本海軍は、英国に指導員と機材の提供を要請、それに応えてアヴロ504K練習機、フェリクストゥF.5飛行艇、ブラックバーン・スウィフトとともに、クックー6機が日本に売却された。
本機と英国での運用実験データを手にしたことで、日本海軍は航空雷撃の基礎を学ぶことができた。また、英国使節団には本機の開発スタッフであるハーバート=スミスも参加しており、彼の指導を受けた三菱の技術者がその後の日本の航空工業を支えていくことになる。
日本海軍が購入した機体はヴァイパーエンジン搭載型で、集合排気管を機体下面まで延ばし、排気熱で魚雷のエンジンを暖気するようになっていた。
本機と英国での運用実験データを手にしたことで、日本海軍は航空雷撃の基礎を学ぶことができた。また、英国使節団には本機の開発スタッフであるハーバート=スミスも参加しており、彼の指導を受けた三菱の技術者がその後の日本の航空工業を支えていくことになる。
日本海軍が購入した機体はヴァイパーエンジン搭載型で、集合排気管を機体下面まで延ばし、排気熱で魚雷のエンジンを暖気するようになっていた。